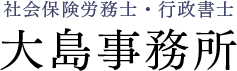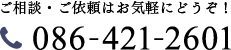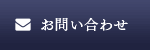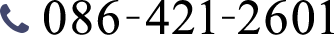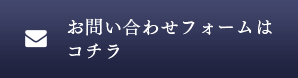お知らせ
家事代行者の「労災認めて」妻急死の夫が国に労基法の「例外」撤回求め7年 近く地裁判決
お知らせ2022.09.08
長時間の家事労働の後に低温サウナで亡くなった家事労働者の過労死認定を求めて
7年にわたり国と闘っている裁判の判決が今月29日東京地裁で判決が言い渡されます。
その家事労働者だった女性は、死亡当日の朝まで1週間泊まり込みで家事労働
24時間の拘束で、午前5時前に起床、2時間おきのおむつ替えや家事をこなし、
夜も高齢者のベッド脇に布団を敷き休む生活だったとみられています。
依頼者である高齢者の家族から介護や調理方法を逐一指示されたとのこと。
家事労働者の夫は、過労死と考え、労働基準監督署に労災保険の支給申請をしましたが、
労働基準法(以下「労基法」という)は「家事使用人」には適用しないという理由で「不支給」に ...
労基法では、「家事使用人」と呼ばれる家政婦(夫)など家事労働者については、
「適用しない」と明記されています。
上級庁に審査請求・再審査請求をしましたが、すべて却下
そこで、5年後の2020年に不支給決定の撤回を求めて国を提訴しました。
なぜ家事を担う人に労基法を適用しないのか?
厚生労働省は「労基法の制定時は家庭内に国の規制を及ぼすのが困難と判断したのでは」(担当課)と推測
労基法は、戦後間もない1947年(S22年)に制定されています。
夫の代理人の指宿昭一弁護士は、次のように指摘しています。
「かつては長期間自宅内に住み込み、家族同様の扱いだったが
今は労働者として家庭に働きに行く。法律で保護しないのは、合理性を持たない」
亡くなった家事労働者の女性も、訪問介護・家事代行サービス会社から派遣されていました。
さて、判決は如何に?
70年以上も変わっていない労基法の除外規定にメスが入るのでしょうか?
注視していきたいと思います。
【労働基準法と家事労働者】
労基法は労働時間の上限や残業の際の割増賃金の支払い、けが・死亡時の補償など雇い主が最低限守るべき条件を定めた法律。法律用語で「家事使用人」と呼ばれる家政婦(夫)ら家事労働者については「適用しない」と明記している。1947年の施行以来、規定は変わっていない。
関連記事
-
コラム新着情報
世界主要国「解雇しやすさ」ランキング…解雇しにくい国でお馴染みの日本、驚愕の順位
ツイッター社、アマゾン、メタ……米IT大手による大量解雇が話題になっています。 アメリカなどに比べ、日本では解雇規制が厳しいというのが一般的な認識だと思われます。 しか...
お知らせ加藤厚生労働大臣会見概要(令和4年10月14日)
閣議報告:・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案を閣議決定・自殺総合対策大綱および自殺対策白書を閣議決定・労働安全衛生法令に基づく作業主任者の常駐規制の見直...
お知らせコラムそれ不当解雇かも! 正当な解雇と不当解雇の違い
不当解雇にも、法で解雇規制がかけられているものと、そうでないものがありますが、法で解雇制限が明記されているものは下記のとおりです。.<労働基準法>・業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!