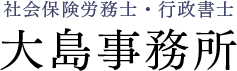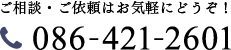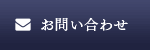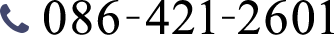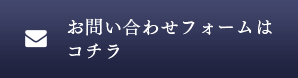お知らせ
雇調金特例、9月末まで延長へ 労働移動阻害の副作用も
お知らせ2022.05.30
政府は新型コロナウイルス禍に伴う雇用調整助成金(雇調金)の特例措置を9月末まで延長する方向で最終調整に入った。6月末までの期限を3カ月延ばす。全業種が対象のままで助成水準も変更しない。一時的な支援のはずの特例は延長を繰り返している。足元の物価上昇も延長理由とするなど目的が変質しつつある。成長分野への労働移動を阻害するなど副作用の懸念も強まる。
雇調金は企業が従業員に払う休業手当を助成する制度だ。通常は1人1日約8300円の上限額を特例として最大1万5000円に引き上げている。企業は従業員を解雇せずに休業させやすくなり、コロナ禍でも失業率の上昇を抑えてきた。
.
経済活動は再開の兆しがみられるが、入国制限などが続き、宿泊や飲食、小売りなどはまだ経営環境が厳しい。ロシアによるウクライナ侵攻後、物価高や円安が経済再開の足かせになるとの懸念も強まり、雇用の下支え策を継続する。
コロナ対応として2020年に始まった特例の位置づけは変わりつつある。本来は経済の大きなショック時に雇用を一時的に守るのが目的だ。だが政府は原油価格や物価の高騰などの影響による経済対策にも活用を決めるなど、支援が常態化している。
欧米各国はコロナ下で導入した雇用維持策の廃止、縮小に踏み出している。米国は中小企業に雇用維持を促す「給与保護プログラム」(PPP)の受け付けを21年5月で終えた。英国も雇用維持策を21年秋に終えた。ドイツは制度自体は続けているが、新規申請は激減した。
厚生労働省は雇調金などにより20年4~10月の失業率(平均2.9%)を2.6ポイント程度抑える効果があったと試算する。その後も失業率は最大で3%台で推移し、一時5%超の英国や8%超のフランスなどと比べて低く抑えてきた。
東京商工リサーチによると、特例を活用した上場企業は22年3月末時点で845社に達した。業種別では製造業が最多の329社で、外食を含む小売り(164社)、観光などのサービス(159社)と続いた。ANAホールディングスの631億円、オリエンタルランドの300億円など、訪日客減少の影響が大きい企業が多く受給した。
.
一方で財源の枯渇が深刻化している。雇調金は雇用者などが支払う雇用保険料などを財源としており、支給拡大に伴って財源が足りなくなった。一般会計から繰り入れる異例の対応を余儀なくされている。回復が進む業種は対象から外すなどの措置もない。
コロナ禍の企業支援をめぐっては政府系金融機関による実質無利子・無担保融資なども延長が繰り返されている。過度な支援が続けば労働移動を阻害し、企業の新陳代謝を停滞させるなど、かえって成長の足かせになる副作用も指摘される。経済活動の正常化に伴って縮小すべきだとの意見が強まっている。
政府は課題を踏まえ、今秋以降は特例措置を縮減して通常の支給要件へと徐々に戻す方針だ。あわせて業種別の支援策や労働移動の促進策も検討する。
.
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA254880V20C22A5000000/?unlock=1
関連記事
-
お知らせ
雇調金特例、延長へ 政府
政府は26日、企業が従業員に支払う休業手当の一部を助成する雇用調整助成金(雇調金)の特例措置について、延長する方針を決めた。6月末に期限を迎えるが、コロナ禍と物価高騰が中小企業に与える影響を考慮した。...
お知らせ雇用調整金「雇用悪化しない限り7月以降は元に」厚労相
17日の衆院予算委員会で、自民党の田畑裕明氏が、休業手当を支給した企業を支援する雇用調整助成金(雇調金)について質問しました。.1人あたりの上限額15,000円/日、助成率を最大100%に引き上げてい...
お知らせコラム雇用調整助成金、9月に財源枯渇か 雇用保険料の見直し検討本格化
新型コロナウイルスの感染拡大で、「雇用調整助成金(雇調金)」の財源が底を突きかけています。 雇用調整助成金は、コロナ禍での雇用維持のため、支給率を引き上げたり、上限額を増額したり、コロナ特例...
ご相談・ご依頼はお気軽にどうぞ!